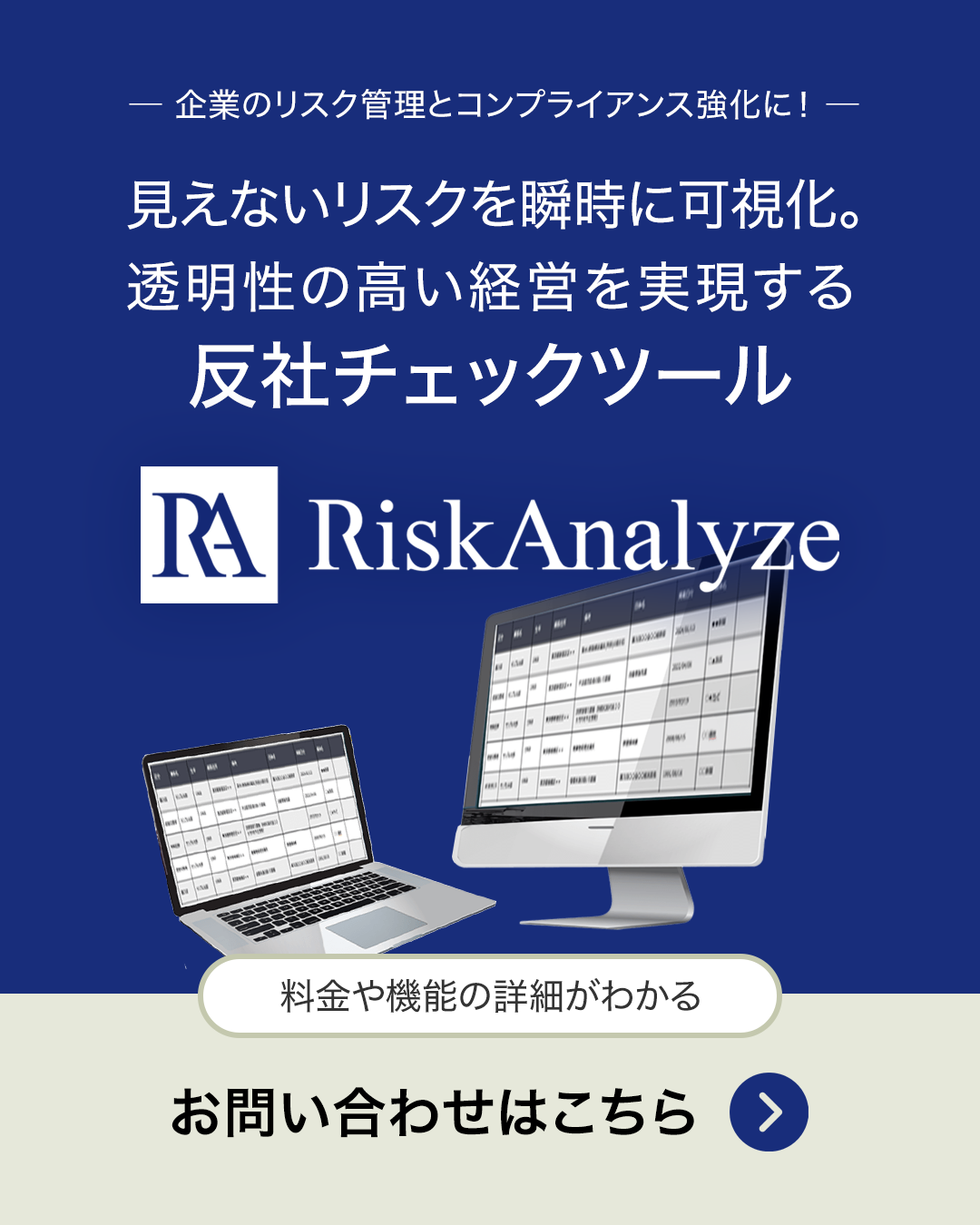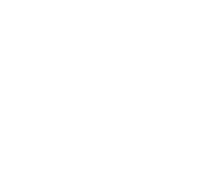ひとり担当者への依存を脱却。年間3,000件の網羅的なチェックを全社で実現

不動産の売買、賃貸管理、そして不動産特定共同事業(不動産小口化)など、不動産資産と金融資産の融合を目指し、価値創造ソリューションをサービス提供する株式会社エール。
都内を中心とした収益不動産の開発および売却、不動産オーナー様が所有する物件の管理・運営、不動産小口化商品の販売など、同社は、顧客・取引先との契約を取り交わす際のチェックと、海外も含めた入居希望者に対するチェックが求められており、厳格なリスク管理体制を必要としていました。
新聞記事閲覧サービスを用いた従来の反社チェックは、特定の担当者に業務が集中する属人的な運用となっており、大きな負担が課題となっていました。さらに、検索結果には多数のノイズ情報が含まれ、目視での取捨選択に多くの時間を要したことから、繁忙期には「反社チェック待ち」の契約が増えるなど、スムーズな契約進行を妨げる要因にもなっていたのです。
こうした状況を抜本的に改善するために導入したのが、反社・コンプライアンスチェックツール「RiskAnalyze」でした。
シンプルで直感的なUIと高精度な検索結果により、各担当者が自らチェックを実施できる体制を構築。従来は1件あたりにかなりの時間を要していた作業が数分単位に短縮され、効率化を実現しました。その結果、年間3,000件にもなるチェックの作業時間は大幅に削減。さらに、継続取引先を対象とした年1回の定期スクリーニング(継続取引先の年1回の再チェック)も実現可能となりました。
今回は、大幅な業務改善を実現した総務部の大床様と鈴木様に、導入前の課題からRiskAnalyze導入の背景、そして属人化から脱却した全社的な反社チェック体制の構築までを詳しく伺いました。
業務負担の集中とコスト課題を解消。RiskAnalyzeを選んだ理由
――RiskAnalyze導入以前、反社チェックはどのように実施されていたのでしょうか?
大床:導入前は、総務部の鈴木が一人で新聞記事閲覧サービスを使ってチェックを行っていました。不動産の売買相手や入居希望者、調達先など件数は多く、また他の業務と並行しながら一人で対応せざるを得ず、大きな負担となっていました。依頼者側も鈴木の都合を待つ必要があり、業務が滞ることもありました。
――ツールを導入したきっかけはなんだったのでしょうか?
大床:最初にRiskAnalyzeを知ったのは、「不動産特定共同事業(不動産小口化事業)」を始めるにあたり、本人確認サービスとして導入したのがきっかけでした。サービスの説明を聞き、「自分たちの取引先チェックにも役立ちそうだ」と感じ、導入の検討を進めました。
――なるほど、導入当時の課題としては先ほどお話してくださった「効率化」が一番だったのでしょうか?
大床:そうですね。課題はやはりチェック作業の非効率さと、担当の鈴木に業務負荷が集中してしまっていたことです。
鈴木:はい。新聞記事閲覧サービスを使ったチェックは非常に手間がかかっていました。特に、検索するとノイズが何百件も表示されることがあるため、表示結果を目視で確認して関連情報を選別する必要があり、この作業に膨大な時間を費やしていました。
それだけではなく、検索演算子を使いこなす必要があることや、IDごとの契約のためコストを考えると複数アカウントを持つことも難しく、どうしても私一人に業務が集中してしまう状態でした。
その結果、本来やりたかった年1回の再チェックもできていなかったんです。こうした背景から、「誰でも簡単に、精度高くチェックできる体制」を整える必要があると考えました。
――RiskAnalyzeをお選びいただいた理由は何だったのでしょうか?
大床:決め手は三つあります。1つめは「シンプルな操作性」です。誰でも使える点が導入の大きな後押しとなりました。2つめは「検索件数に応じた料金体系」で、コストを抑えながら全社で利用できる体制を構築できました。3つめは「検索結果の質の高さ」です。反社チェック専用のデータベースを使っているためノイズが少なく、「該当なし」と明確に表示される安心感がありました。
導入にあたり複数のツールを比較検討しましたが、最も実務に適していて使いやすいと判断し、RiskAnalyzeの導入を決めました。
全社横断の反社チェック体制を構築 年間3,000件を網羅する運用へ
――実際に導入してみて、どのような変化がありましたか?
鈴木:一番大きな変化は、担当者自身でのチェック作業となったことで、私の作業負荷が解消されたことです。また、RiskAnalyzeはシンプルなUIで直感的に使えるため、担当者自身が直接反社チェックできるようになり、反社チェック待ちによる稟議や審査が滞ることはなくなりました。ノイズ情報も出なくなり作業スピードが大幅に改善したことも大きいです。以前は依頼から結果が出るまでかなりの時間を要した作業が、今では数分で終わります。
大床:さらに、社内ルールに基づいた統一的なフローを確立することもできました。当初、チェック件数は例年の年間1,000件程度を想定していましたが、社内ルールが統一化された状態で運用を行った結果、実際には約3倍の3,000件のチェックが必要だと判明しました。作業時間を大幅に減らせただけでなく、チェックの取りこぼしも減らすことができ、現在は網羅性の高い反社チェックが実現できています。
――なるほど。では、チェックの対象について伺えますでしょうか?
大床:RiskAnalyzeを用いて、事業・取引・人材という3つの接点すべてにおいて反社チェックを徹底し、全社レベルでのリスク管理体制を実現しています。
① 不動産業における顧客・契約相手の確認
不動産売買・不動産賃貸・不動産小口化商品の販売など、すべての不動産取引プロセスでリスク確認を実施しています。
不動産売買では、土地や建物の売主・買主といった契約当事者の確認で主に利用しています。不動産賃貸では、入居希望者様自身はもちろんのこと、状況により、同居される方や勤め先などもチェックの対象としています。また最近は、海外の入居希望者様も多いのでRiskAnalyzeの海外情報検索で一緒にチェックを行っています。
② 取引先・外注先へのリスク対策
資材等の調達先や業務委託先など、取引金額の大小にかかわらず、取引先全般を対象にチェックを行っています。
③ 人事領域への活用
採用候補者や社員に関するリスク確認にもRiskAnalyzeを利用しています。
人事情報の扱いには特に配慮し、RiskAnalyze内で部署ごとにアクセス権限を細かく設定しています。
――なるほど。チェックのフローについても伺えますでしょうか?
大床:RiskAnalyze導入後は担当者自身でまずチェック作業を行う体制に変わったため、従来よりも早く完結できるようになりました。具体的な流れとしては、次のような手順です。
チェック実施の流れ
①ログイン:
各担当者がシステムにアクセス。操作はシンプルで、専門知識がなくても扱いやすい設計です。
②検索実施:
法人であれば会社名、個人であれば氏名を入力し、ワンクリックで検索を実行します。
③結果の確認:
検索結果を確認し、リスク情報がある場合には必要に応じてRiskAnalyzeと連携しているG-Search上でも内容を確認し、その内容に応じて対応を進めます。
④該当なしの場合:
結果が「該当なし」であればその時点で手続き完了。ノイズの少ない結果表示により、記事選別作業が不要となり、処理がスムーズに進みます。
⑤該当があった場合:
結果がヒットした場合は、社内の判断基準に基づいて内容を精査。RiskAnalyzeではリスク情報が「暴力団」「特殊詐欺」「一般」などの区分別に提示されるため、どのカテゴリに注意すべきかを明確に判断できます。
⑥最終判断・エスカレーション:
必要に応じて、生年月日など追加情報をもとに同姓同名の可能性を確認。最終的な判断は、総務部の責任者と相談のうえ決定します。
――では、取引の判断基準はそれぞれ異なるのでしょうか?
大床:いいえ、取引や契約の内容で判断基準が異なることはありません。理由は、当社独自の判断基準を設定する際、RiskAnalyzeでカテゴリ分けされたリスク情報に基づいて、社内条件を設定しました。その結果、取引対象が異なっても、社内では統一の基準でリスク判断とエスカレーションを行っています。一例として、表示された記事の経過年数や、同姓同名の別の人物ではなく、対象者本人の情報であるかといったことを注視しています。
このように、リスク情報に関する記事が表示された場合は社内ルールに基づき、各自が記事の内容を総合的に考慮しつつ、判断が難しい場合は、総務部に相談のうえ、総務部責任者が最終判断を行っています。このように、区分・基準・本人確認の3つを軸に、誰が対応しても同じ判断ができる一貫したリスク評価体制を整えています。
「全件チェック」を現実に。年1回の定期スクリーニングで網羅性を確立
――RiskAnalyzeをご導入いただいてから定期スクリーニングも実施されたと伺ったのですが、いかがでしたでしょうか?
大床:そうなんです。今までやりたくてもできなかった「継続取引先の年1回の再チェック」にも取り組めるようになりました。新聞記事閲覧サービスを使っていた頃は、例えば300件あれば300回手動で検索しなければならず、現実的に難しかったのですが、RiskAnalyzeでは一括検索機能を活用して法人・個人をまとめてチェックできます。
実際、初回の定期スクリーニングでは、対象者の選定に少し時間がかかりましたが、リストさえ整えば、入力から結果確認まではあっという間でした。結果として、網羅性と効率性の両立が実現できたことが、今回の定期スクリーニングで一番の成果だったと思います。
――反社チェックの導入やRiskAnalyzeの利用を検討している企業に向けて、アドバイスがあればお願いします。
大床:やはり、反社チェックに特化している点が一番の強みだと思います。多くの企業のご担当者様がご苦労なされているのではと感じるのは、反社チェックと全く関係のない記事まで大量に出てしまうノイズへの対応です。RiskAnalyzeはその点が本当に優れていて、無関係な情報が出てこないため、判断のスピードが圧倒的に早くなります。
また、UIがとてもシンプルで、何を入力すれば結果が分かるのかが直感的に理解できる設計になっているのも大きな利点です。特別な知識がなくても操作できるので、誰でもすぐに使いこなせる。だからこそ、現場の担当者が自ら判断できる体制を作りやすいと思います。
結果的に、効率と正確性を両立できる実務的なツールとして、同じように不動産取引や顧客対応のスピードが求められる企業には特におすすめできます。
――ありがとうございます。弊社のサポート体制はいかがでしょうか?
大床:本当に丁寧で親身にご対応いただきました。私たちは反社チェックの専用ツールを導入するのが初めてだったので、最初は「どの項目をどのようにチェックすればいいのか」といった基本的な部分から検討を進めていました。そうした中で、CS担当の方には「ここは重要です」「こういう設定をしておくと運用しやすいですよ」といった具体的なアドバイスをしていただきました。電話やオンラインで何度も打ち合わせを重ねながら、設定を進めてくださったおかげで、今ではとても使いやすく、的確な判断ができる仕組みが整いました。特に感謝しているのは、権限設定まわりのサポートです。
入居者情報や人事情報など、全員が自由に見られる状態では情報管理上のリスクがあるため、「どの部署がどの範囲まで閲覧できるか」を細かく分けて設定する必要があったのですが、そこも丁寧に一緒に考えていただき、安心して運用できる環境ができました。
――属人化していた業務を分散し、誰もが自らのタイミングで正確なチェックを行える体制を整えたエール様。その取り組みは、単なる業務効率化にとどまらず、企業全体で「リスクと真摯に向き合う文化」を育む一歩となっています。
本日は、導入の背景から運用の工夫、運用方法、社内ルールの整備、そして定期スクリーニングによる全社的なリスク管理体制まで、幅広くご紹介いただきありがとうございました。RiskAnalyzeは、これからもエール様のリスクマネジメントを支えるパートナーとして伴走してまいります。