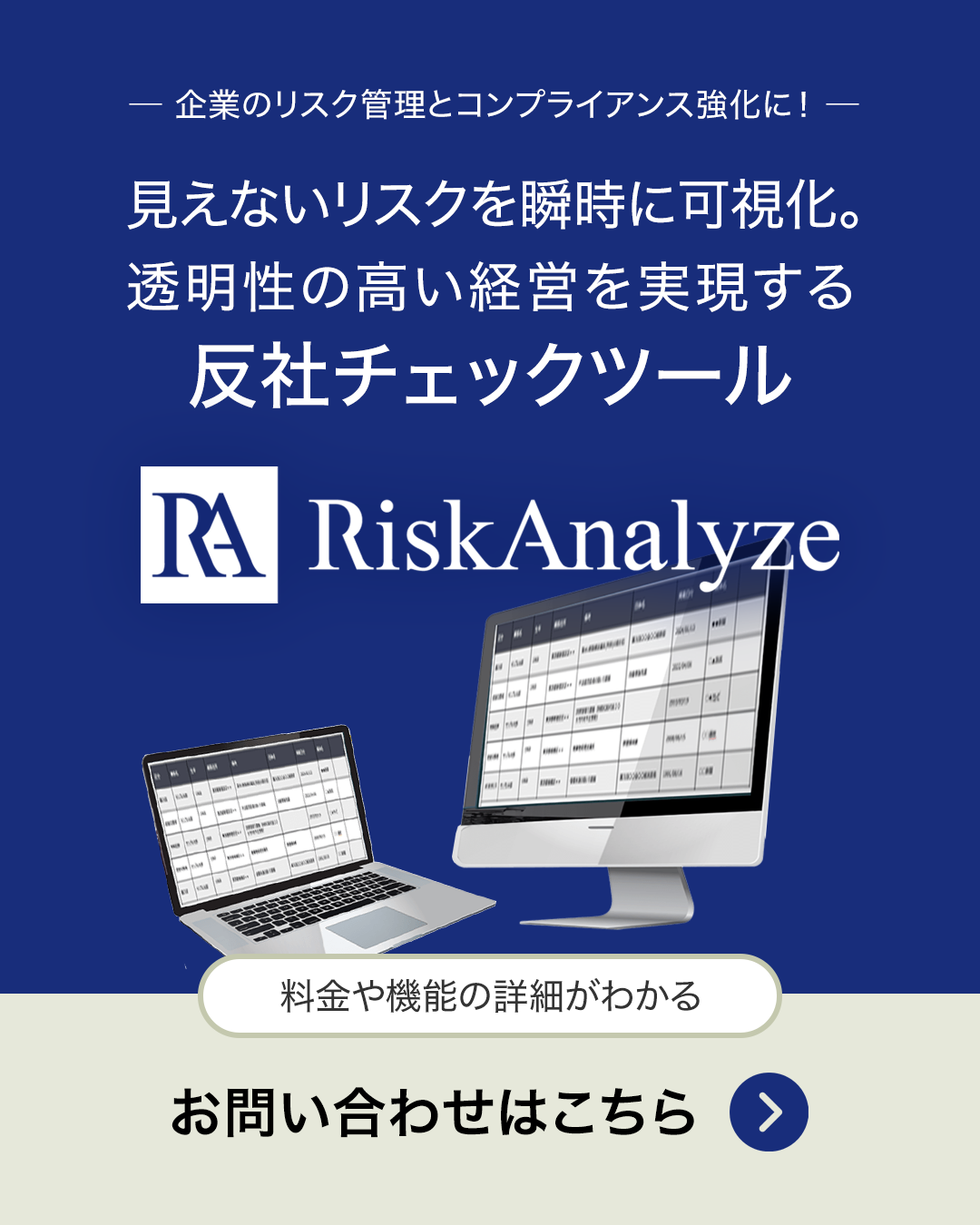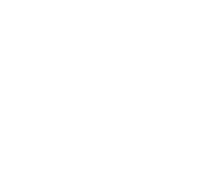“見るべき人をしっかり見る” ブルーモ証券が選んだ反社チェックの最適解とは?

2022年に設立されたブルーモ証券株式会社は、個人を対象に米国株・ETFの投資サービスを提供する新興の証券会社です。
反社会的勢力との関係遮断やマネーロンダリング対策といったリスク管理体制の整備は、金融事業者としての責務であり、同社でも創業当初から取り組みを進めてきました。 そうした中で課題となったのが、限られたリソースの中でいかに効率的かつ実効性の高いチェック体制を構築するか。同社ではAPI連携を活用し、リスクチェックを自動化することで、属人性を排除しつつリスクのある案件には確実に対応できる運用体制を整えています。今回は、証券業務オペレーション構築を統括する吉岡様に、導入の背景や具体的な運用設計、そして今後の展望についてお話を伺いました。
導入初期から“仕組み化”を重視。API連携と網羅性が決め手に
――導入の背景について教えてください。
吉岡:ブルーモ証券では、サービス開始当初から社内の反社チェック体制の整備を着実に進めてきました。証券会社として、反社会的勢力との関係遮断やマネーロンダリング対策は当然の責務であり、体制の構築は不可欠なものだったからです。
当時は開発リソースや予算も限られていたため、複数のツールを組み合わせるよりも、必要な情報を一括で照会できるシンプルで拡張性のあるサービスを探していました。そうした背景もあり、RiskAnalyzeのように即時性が高く操作性も優れたツールは非常に魅力的だったので導入を決めました。
――導入を決めたポイントは何だったのでしょうか?
吉岡:主に3つあります。第一に、自社システムとのAPI連携が可能で、チェック作業を自動化できたこと。第二に、国内のデータだけでなく金融機関に犯罪収益移転防止法で求められているPEPs(政治的影響力を有する人物)やSanction(制裁リスト)情報など、国際的なリスク情報にも対応していたこと。
そして第三に、最終的なコストを許容できるかも重視しました。
反社情報を提供する公的機関の情報照会サービスや、海外リスク情報に特化したツール、他の金融機関向けツールなども比較対象として検討しましたが、RiskAnalyzeは情報の網羅性とコストのバランスにおいて、特に優れていると判断し、導入を決定しました。
e-KYCからRiskAnalyzeまで、自動スクリーニング
――現在の運用フローを教えていただけますでしょうか?
吉岡:当社では、口座開設時にリスクスクリーニングを自動で実施する体制を整えており、申し込みのタイミングから複数のチェックが順次行われる仕組みになっています。
e-KYCによる本人確認をはじめ、社内データベースとの照合や各種リスクチェックまでを含めて、すべてAPIで連携・自動化されており、確認作業にかかる工数は最小限に抑えられています。
また、新規顧客だけでなく、既存顧客に対しても定期的なモニタリングを実施しており、継続的なリスク管理体制を維持できるよう工夫しています。
“見るべき人”に集中できるから、判断もスピーディに
――リスク情報の確認体制はどのようになっているのでしょうか?
吉岡:検索履歴はすべてAPI経由で自動取得・表示される仕組みになっており、オペレーション側の画面に統合されています。そのため、確認作業自体は非常にスムーズで、一定のスピード感を保ちながら対応できる体制になっています。
――リスク情報がヒットした場合には、どのような対応をされていますか?
吉岡:私たちが重視しているのは、“問題ない人”の通過を効率化し、そのぶん“見るべき人”にしっかりと時間をかけるという運用方針です。該当があった場合には、オペレーションチームが内容を確認し、必要に応じて再検索や情報の追加取得を行いながら、社内で総合的に対応方針を検討しています。ヒット件数自体は少ないですが、確認時には慎重に内容を精査するようにしています。
大事なのは“信用できる情報”。まずは自社に合う形で始めてみてほしい
――RiskAnalyzeに対して、今後の機能追加や改善で期待していることがあれば教えてください。
吉岡:さらに便利になるとしたら“自動モニタリング機能”のような仕組みがあると嬉しいですね。制裁リストも日々更新されますし、検索結果も時間とともに変わる可能性があるので、定期的に再照会してくれるような仕組みがあると助かります。
ただ、一律で全件モニタリングするのはコストや件数の問題もあると思うので、たとえば外国籍の方に絞ってチェックを走らせるなど、フィルター付きで対応できるような仕様だと、現実的かなという気もしています。
――反社チェックの導入やRiskAnalyzeの利用を検討している企業に向けて、アドバイスがあればお願いします。
吉岡:ツールを選ぶときは、結局“ちゃんと信用できる情報が取れるか”が一番大事だと思うんです。RiskAnalyzeについてはその点で安心感がありますし、結果の見やすさや検索のしやすさなど、現場の使い勝手もかなり良いと感じています。
弊社はAPIでの連携でしたが、仮にAPIを使わないケースでも柔軟に運用できる選択肢があるのもいいところです。会社の規模や開発体制に合わせて導入しやすいと思いますし、“できるところから始める”というスタンスでも十分運用できるツールだと思います。