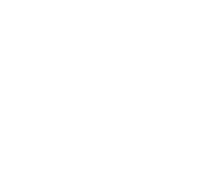SalesForce連携で、月5000件のチェック効率化を実現

ハイブランドからストリートブランドまで、幅広いリユース事業を展開する株式会社STAYGOLD。日々約200件にのぼる仕入れ取引の大半を一般顧客からの買い取りで担い、店頭・訪問・郵送といった多様なチャネルを活用しながら事業を拡大してきました。
同社は「特定事業者」であるリユース業として、一般顧客からの買い取り商談時の全件チェックを通じて厳格なリスク管理を行う体制づくりを目指していました。さらにIPO準備を見据え、コンプライアンス体制の一層の強化にも取り組んでいます。しかし、従来の手作業によるチェックは高コストで現場への負担も大きく、全件チェックは理想でありながら実施できないという課題を抱えていたのです。
その解決策として導入されたのが、Salesforceと連携可能な反社・コンプライアンスチェックツール「RiskAnalyze」です。これにより「ワンクリック反社チェック」が可能となり、従来の方法で全件チェックを行った場合に1商談あたり最大2万円の削減を実現しました。加えて、1件あたり5〜10分の時間短縮も可能となり、店頭スタッフの業務効率化と顧客を待たせない迅速な取引を両立しています。
厳格なリスク管理を全取引に適用することで、同社は顧客体験の向上と社会的信頼を同時に確立し、健全な取引を実現しています。
商談コストを1〜2万円削減、1件あたり最大10分短縮
――RiskAnalyze導入以前、反社チェックはどのように実施されていたのでしょうか?
七井:以前は信用照会ツールを利用し、犯罪収益移転防止法に基づき200万円以上の取引を対象に手作業でチェックを行っていました。しかし、IPO準備や法令遵守の観点から、すべての取引を対象に反社チェックを実施し、暴力団などへの利益供与を未然に防ぐ体制を整える必要があると考え、見直しを進めました。
――なるほど、全取引のチェック実施に向けた業務効率化の改善が導入当時の課題だったのでしょうか?
七井:そうです。手動で全件チェックを行おうとすると、1件ごとにリスク情報を精査する必要があり、膨大な時間と工数がかかると想定されていました。その結果、人的リソースが圧迫され、商談スピードの低下や収益基盤への影響が懸念されたのです。こうした背景から、従来の運用では限界があると感じていました。
――RiskAnalyzeを導入した決め手は何だったのでしょうか?
七井:導入の決め手は、AppExchangeを通じてSalesforceとスムーズに連携できる点でした。これにより一次チェック体制を人の手を介さず自動化でき、店舗スタッフもSalesforce上でボタンをひとつ押すだけで反社チェックが実行できるようになり、負担を大幅に軽減できると判断しました。
――実際に導入されて、どのような効果がありましたか?
七井:業務効率化とコスト削減の両面で、大きな効果を実感しています。
まず業務面では、店舗スタッフによるチェック時間が1件あたり5〜10分短縮され効率化できたことで、お客さまをお待たせすることなくスピーディーに取引を進められるようになりました。加えて、Salesforce上で反社チェックの実績確認やリスト化が自動化されたことで、これまでのように担当者が証跡を残したりリストを付け合わせたりする必要がなくなり、見えない作業負担も解消されています。
コスト面では、従来の方法で全件チェックを行った場合、1商談あたりのコストがシステムの自動化により概算で1〜2万円の削減を実現しています。さらに、リスク情報がヒットした際にはSlackを通じて自動的にコンプライアンス課へ通知され、二次精査までスムーズに連携できる体制を整えたことで、判断の正確性とスピードを両立できるようにもなりました。
――Salesforceとの連携構築で工夫や苦労した点はありますか?
七井:連携自体はAppExchangeのインストールと微調整だけで、2週間ほどで稼働できました。
徹底した社内ガイドラインと取引判断基準
――現在は、全件チェックを実現されているのでしょうか?
七井:はい。買取金額に関わらず、買取が成立したお客さま全員が対象です。弊社では店頭買取だけでなく、訪問買取や郵送買取も実施していますが、いずれの方法であっても全件に対して反社チェックを行っています。
――店頭・訪問・郵送など、それぞれどのようなチェックフローで行われているのでしょうか?
七井:それぞれ、
店頭での買取
お客さまが来店し、買取が決まった時点でリスクチェックを行います。店舗スタッフはSalesforceの画面にお客さまの情報を入力し、「実行」のボタンをクリックするだけでOKです。するとすぐにRiskAnalyzeと連携した結果が表示され、特別な操作をせずにチェックが完了します。
郵送での買取
お客さまから情報提供があった際に、コールセンタースタッフが一次チェックを行います。買取確定前の個人情報開示に抵抗があるお客さまもいらっしゃるため、買取が確定した時点で再度、氏名と生年月日を用いて二度目のチェックを実施しています。
訪問での買取
お客さまから問い合わせがあった際に一次チェックを行い、その後訪問して買取が成立した段階で二度目のチェックを行います。
といったフローで行っております。いずれの方法でもRiskAnalyzeでヒットがあった場合には、Slackを通じてコンプライアンス部へ通知されます。コンプライアンス部では通知内容をもとに、お客さまがリスク情報に該当する同一人物であるかを精査します。その際、基本的にはRiskAnalyzeから参照できる新聞記事の確認をしています。
――なるほど、ありがとうございます。どのような基準で買取可否を判断をされているかも伺えますでしょうか?
七井:はい。犯罪収益移転防止法で定められている暴力団や密接交際者はもちろん、詐欺・窃盗・監禁・性犯罪・殺人といった重大犯罪に該当する場合は取引不可としています。
――監禁や性犯罪など、法律で取引が禁止されてはいない犯罪も買取NGにしている理由は何でしょうか?
七井:監禁や性犯罪といった犯罪は、たしかに法律上で直接「取引禁止」と定められているわけではありません。しかし弊社では、これらすべてを「暴力団に準ずる集団犯罪との関与が疑われるもの」とガイドラインで位置づけ、取引対象外としています。
店頭スタッフからも、リスクチェックの基準が「かなり厳しい」という声が上がっていますが、弊社としては少しでもリスクのある取引は行わない方針をとっています。
効率化と信頼性向上を同時に実現するソリューション
――ありがとうございます。導入を検討している企業に向けてアドバイスがあればお願いできますでしょうか。
七井:RiskAnalyzeは、業務効率化とコンプライアンス体制の強化を同時に実現したい企業にとって非常に有効なツールだと思います。
私たちの場合、Salesforceとの連携によりワンクリックでチェックが完了し、1件あたり5〜10分の時間短縮や1商談あたり1〜2万円のコスト削減につながりました。Slack通知を活用した二次精査体制によって、正確性とスピードも両立できています。
以前は高額取引に限定していたチェックも、全件対象へと拡大し、厳格な社内ガイドラインに基づいた運用が可能になりました。導入も短期間でスムーズに進み、UIもシンプルで現場から好評です。
取引の信頼性を高め、安心できる体制を築きたい企業には、ぜひおすすめしたいです。