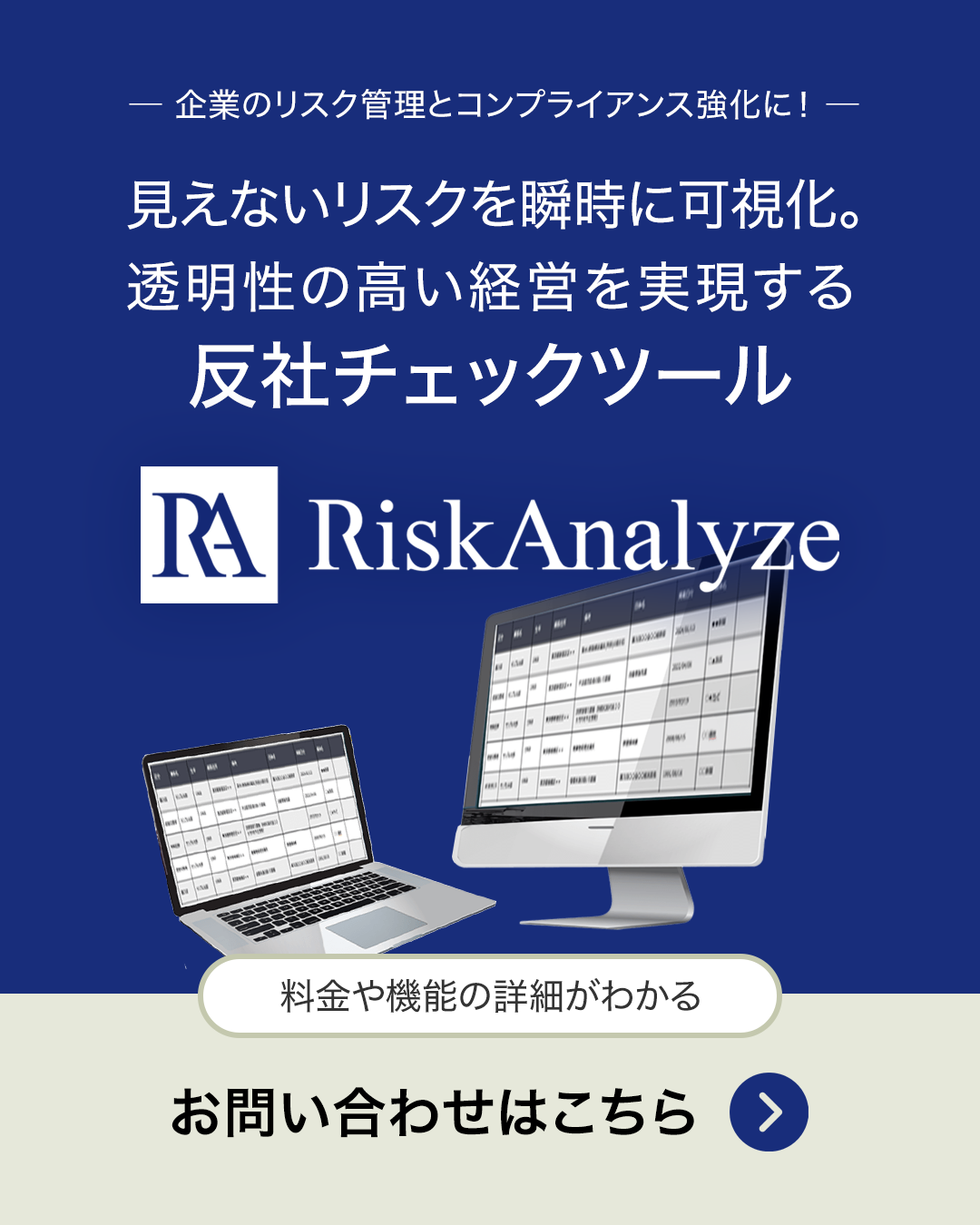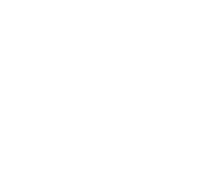Salesforce連携で反社チェック業務を84%削減。セーフィーのリスク管理体制とは

クラウド録画サービス「Safie(セーフィー)」を展開するセーフィー株式会社。法人を中心とした防犯カメラの提供を通じて、安全・安心な社会インフラの構築を支えています。2021年の上場以降、取引先やパートナー企業との関係性においても、コンプライアンスとリスク管理の徹底がより一層求められるようになりました。
当初は新聞記事閲覧サービスやGoogle検索による手動運用に加え、クラウドRPAツールを活用した効率化にも取り組んでいましたが、Salesforceの開発環境との連携課題や運用面の不安定さから、さらなる最適解を模索。そして2025年、Salesforceとの高い親和性や独自のリスクデータベースを評価し、反社チェックツール「RiskAnalyze」を導入しました。 今回は、法務部門の河原様・大島様、業務システム部門の石塚様に、導入前の課題やツール選定の経緯、現在の運用体制と成果、そして今後の展望について詳しく伺いました。
Salesforce連携の壁とRPAの限界。セーフィーがRiskAnalyzeを選んだ理由
――RiskAnalyze導入前は、どのように反社チェックを行っていたのでしょうか?
河原:上場当時は新聞記事閲覧サービスとインターネットを使って、受注のたびに企業名や代表者名を手作業で検索していました。Salesforceに受注情報が入ると、法務が新聞記事閲覧サービスで検索し、問題なければチェック完了、という流れです。ただ、事業の拡大とともにチェック件数が増え、この運用には限界を感じていました。
――手作業での運用に限界を感じたとのことですが、その後はどのような対応をされたのでしょうか?
河原:はい。当時の前提として「Salesforceと連携できるサービスを使いたい」という思いがあり、最小限の工数で始められそうなクラウドRPAツールを導入し新聞記事閲覧サービスとSalesforceの連携をしていました。しかし、導入時にトラブルがあったり障害の発生頻度が高かったりしたことから当初の見込みよりも保守の工数が高くなってしまい、継続運用に限界を感じたため、乗り換えを決断し複数のツールを検討しはじめました。
――どのような観点でツールの検討をされたのでしょうか?
河原:大きく2つあって、1つはSalesforceとの連携のしやすさ。もう1つは、ノイズ情報の混ざっていない反社チェックに特化した独自データベースであるかです。クラウドRPAツールを導入した際にSalesforceとの連携がスムーズにできなかった経緯があるので、今回はその反省を踏まえて業務システム部のメンバーにも初期段階から加わってもらい、トライアル環境やAPI仕様を確認しながら、実装の難易度や工数を事前にしっかり見極めたうえでRiskAnalyzeの導入を決めました。
石塚:Salesforce側の制約も多い中で、RiskAnalyzeはAPIを活用して柔軟に自社のオペレーションに組み込むことができたのが大きな魅力でした。RPAのようにUI変更に弱い仕組みではなく、システム連携に強い構成になっているのがいちばんの決め手でしたね。
――Salesforce連携のしやすさはいかがでしたか?
石塚:はい。「RiskAnalyze for Salesforce」のパッケージ内に含まれる機能を利用することで、実装は非常にスムーズでした。先程もお伝えした通り既存の業務フローをほとんど変えずに導入できたのは、大きなメリットです。Salesforceの設定画面にログイン情報などを入力するだけで連携が完了するので、開発リソースも最小限で済みました。
RiskAnalyzeでの自動検索とSlack連携で即対応。月84%の業務削減を実現した運用体制とは
――現在の反社チェックフローについて教えてください。
河原:Salesforce上で受注が確定したタイミングで、自動的に反社チェックが走るようにしています。RiskAnalyzeの検索結果に記事が1件以上ヒットした場合は、Slackに通知が飛ぶよう設定しており、法務が内容を確認します。
大島:通知にはRiskAnalyzeのURLがついており、すぐに詳細を確認できます。リスク情報は「暴力団」「密接交際者」「一般犯罪」などにカテゴライズされているので、記事の内容を読まずともリスクの重さを把握しやすい構成になっています。
――導入後、どのような効果がありましたか?
河原:平均1件あたりの確認時間は5分から1分に短縮。結果として、月間作業時間は1300分から210分に。84%の工数削減を実現できました。
大島:私一人で反社チェックを実施しているのですが、体感としてもすごく業務が効率化されて楽になりました。以前は検索に時間がかかり、内容確認も大変でしたが、今は即時に確認・判断できるので、他業務にも集中できます。RiskAnalyzeを導入して、ほんとうによかったです。
――以前使用されていた新聞記事閲覧サービスとの大きな違いはなんでしょうか?
河原:大きな違いはRiskAnalyzeでは履歴が残ることです。新聞記事閲覧サービスでは都度検索が必要なので、上司に最終判断を仰ぐ際など、再度検索するたびに見出しや記事を見る必要があるため、その度に課金が発生していました。一方でRiskAnalyzeは検索履歴が残るため、再確認も容易ですし、記録としても正当性を示しやすいのが利点です。
採用候補者も対象に。上場企業ならではの厳格さ
――採用時にも反社チェックを行っていらっしゃるんですよね?
河原:はい。採用候補者に対しても、最終面接の直前に適性検査とあわせて反社チェックを実施しています。これは内定を出す前の重要なステップで、単に反社会的勢力との関係の有無だけでなく、過去に問題を起こしていないか、といった点も含めて調査します。適性検査か反社チェックのいずれかで問題が見つかれば、最終面接の結果として不採用とする判断を行います。
――どのような方法でチェックされているのでしょうか?
河原:顧客向けのチェックとは異なり、採用候補者の管理にはSalesforceとは別のツールを使っています。この採用用ツールとRiskAnalyzeは直接連携していないため、RiskAnalyzeの顧客検索機能を中心にGoogle検索も併用しています。判断基準は比較的厳しめで、「過去に問題行動をしていないかどうか」や「ネット上で炎上した履歴がないか」といったリスク情報も幅広く確認しています。
連携精度と検索効率をもっと高く。セーフィーが期待する次のアップデート
――RiskAnalyzeに今後期待することがあれば伺えますでしょうか?
河原:現状でも業務に十分活用できており特に不満はありませんが、あえて挙げるとすれば、Salesforceとのさらなる連携強化があると嬉しいです。たとえば、チェック履歴のない取引先をSalesforce上で条件抽出し、そのまま一括チェックを実行できるようになると、運用がさらに楽になります。現在は一度新規取引発生時に検索をかけているものが自動一括チェックの対象となっていますが、これがSalesforce内で完結できれば、よりスムーズです。
大島:あと、会社名や代表者名が変更されたタイミングで、自動的に再チェックが走るような仕組みもあると、より安心です。ただ、今も全体的に非常に満足しているため、今後も継続して活用していきたいと考えています。