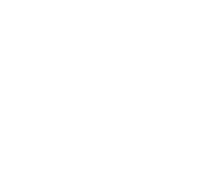「1件10分→30秒」へ。Salesforce連携で反社チェックを自動化し、内製型リスク管理体制を確立

データ最適化と業務プロセス改革を軸に、企業のDXを支援する株式会社オプロ。
同社は、クラウド帳票作成や電子申請・承認ワークフローなどを中心とした「データオプティマイズソリューション」と、サブスクリプション型ビジネスを支える「セールスマネジメントソリューション」の2事業を展開し、行政・金融機関から民間企業まで幅広い顧客の業務効率化を支えています。
上場企業としてコンプライアンス強化に取り組む中で、取引先やパートナーの反社チェック体制も見直しが求められていました。
従来は新聞記事閲覧サービスとネット検索を併用し、チェック1件あたりに10分以上を要し、記事のノイズや証跡保存の方法など、精度と工数の両面に課題を抱えていました。
この課題を解決すべく導入したのが、Salesforceとシームレスに連携できる反社・コンプライアンスチェックツール「RiskAnalyze」。
契約前の取引先チェックを半自動化し、わずか30秒で証跡保存までを完了する仕組みを構築。チェック結果はSalesforce上で一元管理され、外部依存から脱却した“内製型のリスク管理体制”を実現しました
今回は、管理部の飯田様と相田様に、導入前の課題や選定の決め手、運用による効果、そして今後の展望について詳しく伺いました。
RiskAnalyzeで“10分→30秒”、定期スクリーニングも“2カ月→数分”に
――RiskAnalyze導入前はどのように反社チェックを行っていたのでしょうか?
飯田:導入前は、主に新聞記事閲覧サービスとネット検索の2つを使ってチェックを行っていました。
まず新聞記事閲覧サービスで会社名や代表者名を検索し、記事がヒットした場合は内容を確認して、反社会的勢力との関係や懸念がないかをチェックしていました。
同じようにネット上でも同様のキーワードで検索し、関連ニュースや風評情報がないかを確認する二重チェックを行っていました。
――導入時の課題としてどのようなものがあったのでしょうか?
飯田:一番の課題は、新聞記事閲覧サービスやネット上で検索をすると、関係のない情報が大量に表示され、必要な情報を見つけるのに非常に時間がかかっていたことです。
同姓同名の別人や記者の名前、さらにはポジティブニュースなども多数ヒットし、1件あたりの確認に10分ほど要することもありました。さらに、新聞記事閲覧サービスとネットの二重検索を行い、その結果のスクリーンショットを保管する必要があり、業務全体としてかなりの手間と工数が発生し、対象件数が多くなるにつれて負担が増していました。
さらに風評調査では、SNSや口コミサイトなどネット上の情報を手作業で確認する必要があったんです。
こうした非効率な手作業を改善したいという思いが強く、「時間と工数を削減しながら、より精度の高い反社チェックを実現できる仕組みが必要だ」と思っていました。
――RiskAnalyzeの導入の決め手を伺えますでしょうか?
飯田:導入の決め手は大きく分けて、Salesforceとの連携が可能だったことと、コスト面の2点です。
まず、最大の決め手となったのはSalesforceとのシームレスな連携でした。
当社ではもともとSalesforceを中心に顧客情報を管理しており、導入検討の際も「Salesforce上で完結できるツール」を条件に探していました。
RiskAnalyzeはSalesforceと直接連携させてワンクリックでチェックを実行でき、結果も即時に確認できるので、このスピード感が非常に魅力的でした。
さらに、導入時のコスト面でも無理がなく、機能が必要十分で操作もシンプルだった点も大きな決め手です。「Salesforce連携による業務効率化」と「費用対効果」の両立が実現できるツールとして、RiskAnalyzeの導入を決めました。
――ありがとうございます。導入後の変化はいかがでしょうか?
飯田:導入後は、業務効率とチェック精度の両面で劇的な改善が見られました。
一番大きな変化は時間と工数の削減です。
これまでは、新聞記事閲覧サービスとネット検索を使って1件あたり10分ほどかけて検索・確認していましたが、RiskAnalyze導入後はSalesforce上でボタンをクリックするだけ。わずか30秒もかからずチェックが完了するようになりました。
また、従来は検索結果のスクリーンショットを保管する必要がありましたが、現在はRiskAnalyze上で履歴が自動的に記録・管理されるため、手作業の負担も大幅に減りました。
相田:あとは、チェックの精度と質も向上しています。
導入前は同姓同名の別人や無関係な記事が多数表示され、不要な情報を取捨選択するのに時間を要していましたが、RiskAnalyzeでは関係のない情報が排除され、「見るべきものだけを見られる」ようになりました。
これにより、確認作業の集中度が高まり、見落としのリスクも減少しました。
――なるほど、定期スクリーニング(一括検索)もされたと伺ったのですが、変化はありましたでしょうか?
飯田:はい。実は、特に効果を実感しているのが、定期スクリーニングなんです。
以前は外部業者に依頼しており、結果が返ってくるまでに約2ヶ月かかっていましたが、RiskAnalyze導入後は同じ処理が数分で完了します。メールで結果がすぐに届くようになり、過去に検索した情報を再確認する必要もなくなりました。
「もう以前の方法には戻れない」と感じるほど、効率的で実務に即した仕組みになっていると実感しています。
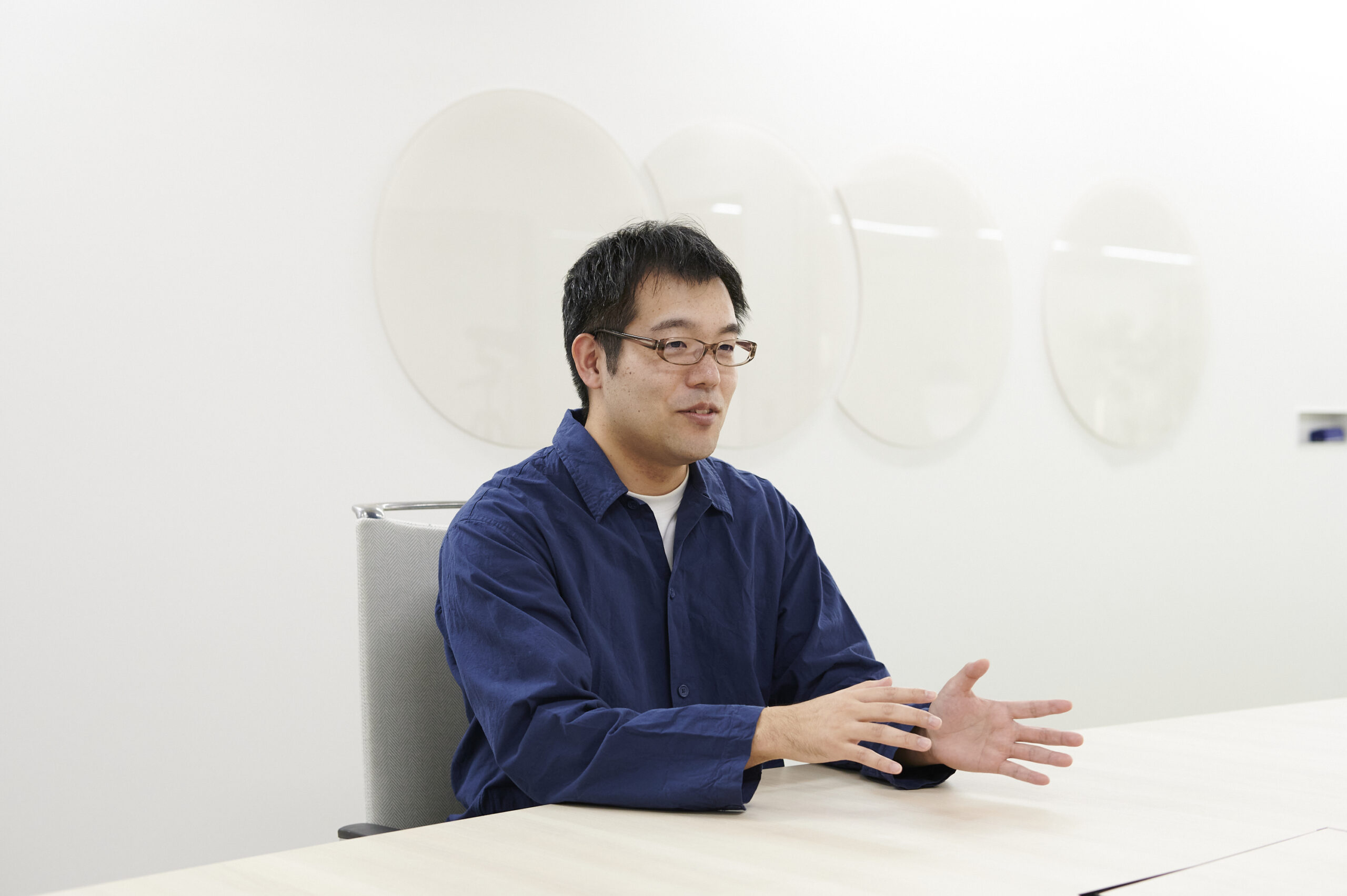
上場企業としての信頼を支える、リスク管理体制の構築
――上場企業として意識していることはありますでしょうか?
飯田:上場企業として最も意識しているのは、社会的信頼を維持するためのリスク管理体制の徹底です。上場企業である以上、「知らなかった」「気づかなかった」では済まされません。RiskAnalyzeを導入したことで、チェックの精度を上げながら効率化を実現できました。
また、自社の風評チェックも定期的に行っています。
上場企業としては、事実ではない情報や誤解を招く投稿が拡散されることもリスクの一つです。
特に採用サイトや口コミサイトなどにおける企業評価についても、定期的に確認し、万が一誤情報があった場合には迅速に対応できるよう体制を整えています。
今後も、企業の透明性と説明責任を果たすために、継続的にリスク管理体制を見直し、改善していくことを意識しています。
――どのようなフローでチェックをされているのかご教示いただけますでしょうか?
飯田:取引先チェックは、新規・既存の双方に対して行っています。
まず新規取引先については、Salesforce上に営業担当者が登録した取引先情報をもとに、直近に登録されたデータを週次で抽出し、レポート機能で一覧化し、管理部である私や相田がまとめて確認しています。チェック自体は、各レコードからワンクリックで実行できます。実施履歴はRiskAnalyze上で自動的に保存されるため、従来のようにスクリーンショットを撮って保管する必要もなくなり、Salesforce上の専用項目でチェック状況を更新する運用に統一しています。
一方で、既存取引先については年に一度、RiskAnalyzeの一括検索機能を用いて定期スクリーニングを実施しています。以前は外部業者に依頼しており、外部業者から返ってきたヒット案件(約100件ほど)を再度社内で精査する必要がありましたが、RiskAnalyze導入後は再チェックの必要性もほとんどなくなりました。
加えて、自社の風評確認も月次で実施しています。RiskAnalyzeにあらかじめ登録されているリスクワードを活用し、上場準備に関する報道や、採用・口コミサイトなどで事実と異なる情報が出ていないかを定期的にモニタリングしています。
――御社におけるエスカレーション対応について伺えますでしょうか?
飯田:懸念情報が出た場合の対応については、まず自分たちで可能な範囲の確認を行い、それでも判別がつかない場合に上長へエスカレーションするという流れを取っています。
RiskAnalyzeの検索結果で「判定あり」と出た際に、同姓同名などで該当人物かどうか判断がつかないケースがあります。そのような場合は、まずGoogle検索などを活用して自分で再度確認を行う、いわゆる二次チェックを実施します。それでも確証が得られない場合には、「これ以上は判断できない」という段階で上長に報告し、「問題なしとして進めて良いか」を確認してから最終判断をしています。
また、リスク情報のカテゴリーによっても対応の優先度を明確にしています。特に、暴力団・準暴力団・過激派・特殊犯罪など、RiskAnalyze上で定義づけられているリスクカテゴリにおいては、取引先や採用のチェックにおいては明確に排除すべき対象として扱っています。
このように、一次チェック・二次チェック・上長確認という3段階のフローを設けることで、判断の属人化を防ぎつつ、組織として一貫したリスク判断ができる体制を整えています。
反社チェックを“仕組み化”へ。効率化の実感と今後への期待
――「RiskAnalyze」の利用を検討している企業に向けて、アドバイスをお願いします。
飯田:反社チェックに時間や負担を感じている企業ほど、導入効果は大きいと思います。手作業では10分以上かかっていた確認が、RiskAnalyzeならワンクリック・30秒以内で完了し、担当者が本来の業務に集中できるようになりました。
また、Salesforceなど既存システムとの連携性も大きなポイントです。導入時はマニュアルを見ながら社内で設定でき、開発工数もほとんど不要でした。チェック結果もシステム上で一元管理されるため、スクリーンショットの保存など手作業による記録も不要になっています。
結果として、時間・手間・リスクのすべてを最小化できるツールだと感じています。反社チェックを「やらなければならない作業」から「自然に回る仕組み」に変えたい企業には、ぜひおすすめしたいですね。
――ありがとうございます。リスク管理体制について展望があれば伺えますでしょうか?
飯田:今後は、採用領域での活用と既存社員・役員の定期スクリーニングの体制化を進めていきたいと考えています。
まず採用面では最終面接段階の候補者チェックにも活用し、採用判断前に懸念情報を迅速に確認できる仕組みを整えたいと考えています。これにより、バックグラウンド確認の信頼性を高めながら、採用リスクの早期発見につなげることができると思います。また、既存社員や役員を対象とした年次スクリーニングも実施予定です。
こうした取り組みによって、リスク管理体制をより強固なものにしていきたいと思っています。