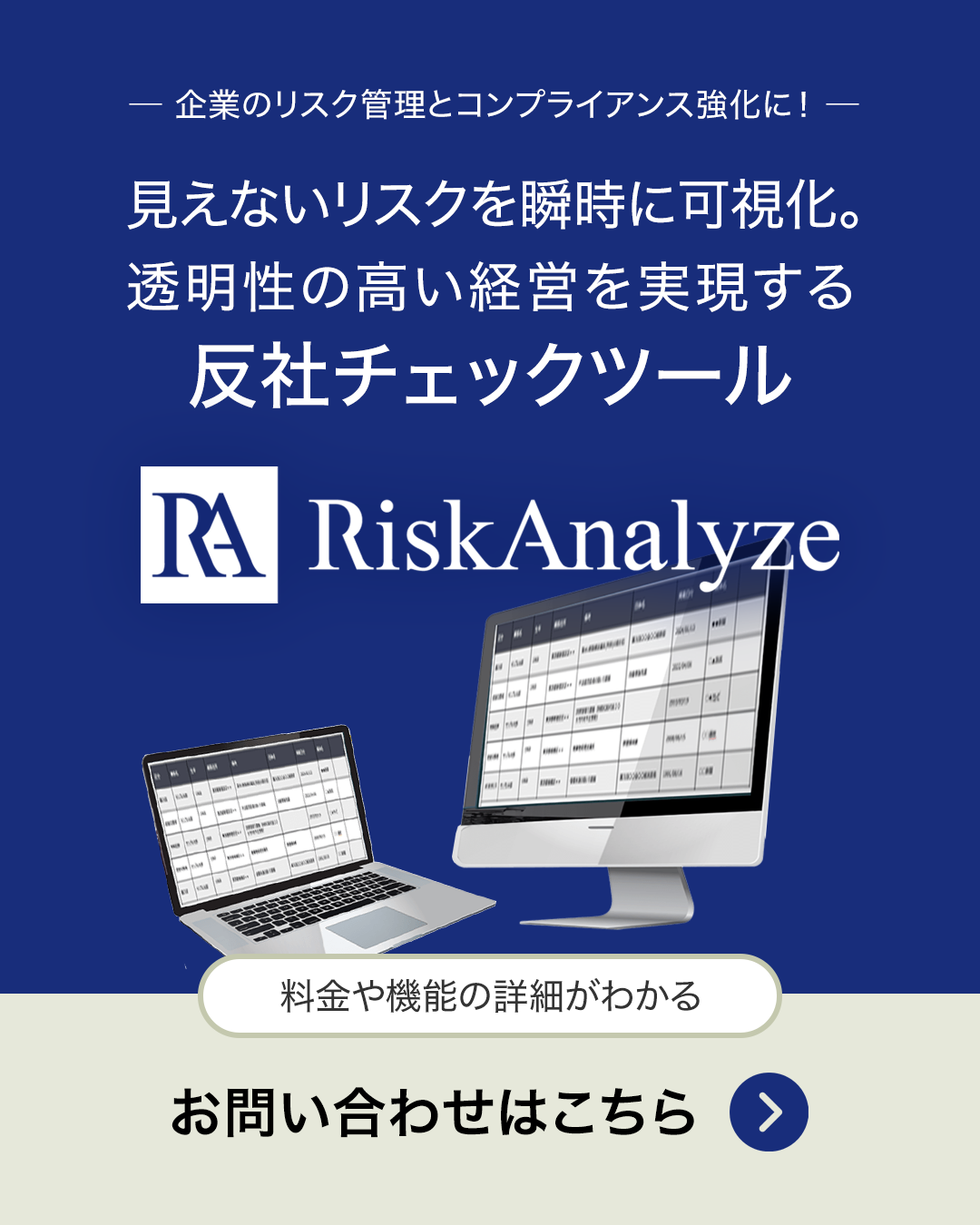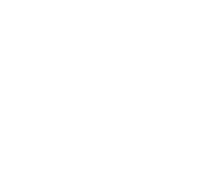年次スクリーニングの工数98%カット。IPO実現の裏にあった、RiskAnalyzeの存在。
住宅ローン比較診断サービス「モゲチェック」や、不動産投資サービス「INVASE」を運営する株式会社MFS。同社は、2024年6月21日に東京証券取引所グロース市場への上場を果たしました。この大きな成功の裏にあったのが、IPOに向けたコンプライアンス対応を効率化するために導入した「RiskAnalyze」の存在です。導入に至った背景、選定理由、そして導入後に得られた具体的な効果を取締役CFOの平山様に伺います。

1件あたりの検索単価より、長期的な価値を重視した。
――RiskAnalyze導入以前に感じていた課題を教えてください。
以前は、新規取引先のみのコンプライアンスチェックを新聞記事データベースやインターネット検索で行っていました。
しかし、IPOを目指すなかで、将来的に証券会社審査において既存取引先を含めた年次スクリーニングや証跡の保存の提出が求められるであろうことは予想していました。従来の方法では、工数とコストが膨大になることは明白です。一方で、システムを自社で開発するのは現実的ではありません。業務負荷を軽減しながら効率的に実現できる方法を模索していました。
そんな折にVC(ベンチャー・キャピタル)から紹介されたのが、RiskAnalyzeでした。リスク情報がデータベース化されているだけでなく、誰でも簡単に検索・確認ができ、保存結果をすぐに提出できる。こんなサービスがあるとは思ってもいなかったので、とても驚いたことを覚えています。
――RiskAnalyze導入の決め手は何でしたか?
導入を決めた理由は3つあります。まず、操作性です。UI/UXがシンプルである点が挙げられます。リスク情報の確認が、氏名や会社名を入力するだけで完了する直感性の高さが魅力でした。
次に情報の網羅性です。新聞記事だけでなく、行政処分情報なども一元的に確認できるため、従来のように複数のソースを使い分ける必要がなくなりました。
そして、コストパフォーマンス。1件あたりの検索単価だけで試算した場合、新聞記事データベースを利用したほうがコストを抑えられるように思えます。しかし、人的工数や情報の正確性、チーム全体のモチベーションまで考慮すると、RiskAnalyze導入による長期的な価値のほうが圧倒的に高いと判断しました。

RiskAnalyzeだけで、IPO審査を通過。
――実際にRiskAnalyzeを利用してみて、どのような効果を感じましたか?
これまでのプロセスがいかに非効率だったかを痛感しましたね。以前は、リスク情報が含まれる可能性が高い記事を選別し、該当記事をすべて読んで判断していました。
現在は、必要情報を入力するだけでリスク情報の有無が即時表示されます。実際、年次スクリーニングにかかる工数を試算したところ、従来の手法と比較して98%の工数が削減されたことがわかりました。
また、リスク情報が統一された形式で提供されるため、属人的な判断を排除し、効率的に稟議を進められる点も非常に有益です。社内での意思決定プロセスもスムーズになりましたね。
――実際のIPO審査ではどのように役立ちましたか?
証券取引所では新聞記事データベースを推奨していますが、今回の審査ではRiskAnalyzeのみを活用して全件チェックを実施しました。反社チェックにおいて、単一サービスで上場した事例を聞いたことがなかったので一抹の不安もありましたが、結果として特段の指摘や追加要望はなく、無事に審査を通過できてよかったです。
想定していた通り、証券会社審査では反社チェックの網羅性、保存されたデータの有無、正確性など細かくチェックされました。既存取引先の年次チェックも実施が必須となりましたが、RiskAnalyzeによりほぼ追加工数なく対応できました。
「RiskAnalyzeとはどういうサービスか」という質問に対しても、KYCコンサルティング社のHP(サービスページ)の説明で対応できたことも、スムーズな審査対応につながったと考えています。
RiskAnalyzeがIPO審査に必要な基準を十分満たしていることが実証され、今後も安心して利用を続けられるという信頼感が増しましたね。
――ありがとうございます。
IPO審査時の反社・コンプラチェックを自分たちの手で行うのは、限界があると感じています。しかもIPOを達成できたからといって、確認作業がなくなるわけではありません。自社の法令遵守を高い基準で守るために、RiskAnalyzeは欠かせない存在になっています。