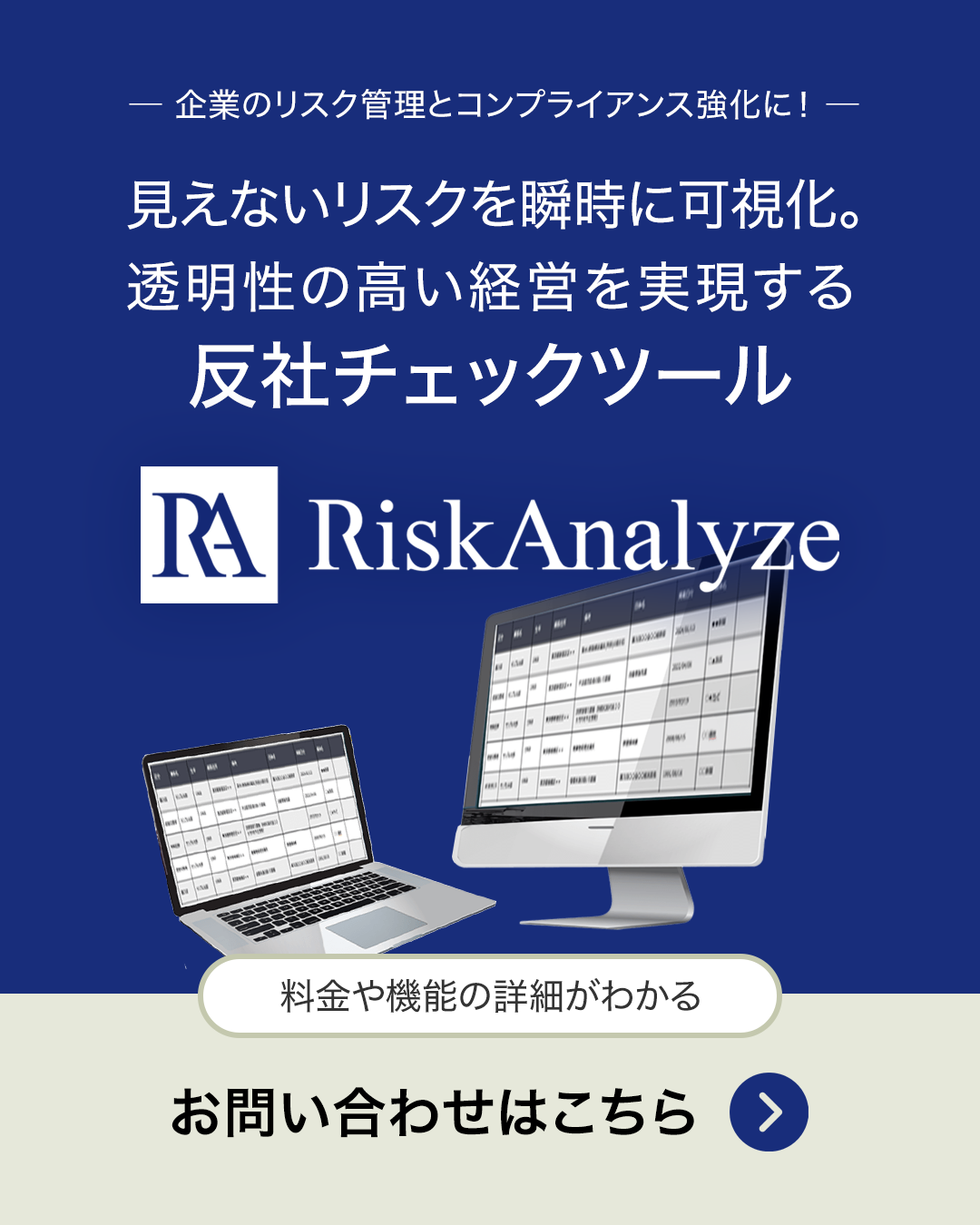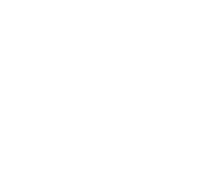“量”と“質”を両立するリスク管理。IPO後も“標準装備”として活躍

レシピ動画サービス「クラシル」で知られるクラシル株式会社。近年では、買い物サポートアプリ「クラシルリワード」やライフスタイルメディア「TRILL」、ライバーの育成・マネジメントを行う「LIVE with」など、多角的な事業展開を進めています。生活者との多様な接点を持つメディア・プラットフォーム企業として成長を続け、2024年にはIPOも達成。
IPOを経た今も、コンプライアンスやレピュテーションリスクへの備えは、経営における重要テーマのひとつです。今回は、コーポレートガバナンス部の木下様に、RiskAnalyze導入の背景や選定理由、実際の運用体制、さらには今後の展望について詳しく伺いました。
わずか1件1分未満の効率性が決め手に。チェック体制の転換点
――RiskAnalyze導入前の課題と、導入を決めた理由を教えてください。
木下:導入は2022年からで、それ以前は新聞記事閲覧サービスを活用してリスクチェックを行っていました。当時は取引先やライバーに対するチェック件数は今ほど多くなかったものの、作業の負担は決して小さくありませんでした。情報ソースは豊富だったものの、1件あたりにかかる作業時間が読みにくく、記事の確認作業によって10〜30分を要するケースもありました。
ちょうどその頃、当社ではIPOを見据えており、今後のチェック件数の増加に備えてより効率的で安定したリスクチェック体制の構築が急務となっていました。こうした背景から、チェックツールの導入を検討し始めました。
――RiskAnalyzeの導入の決め手はなんだったのでしょうか?
木下:最大の決め手は、チェックにかかる時間の短さと結果確認までのスムーズさです。RiskAnalyzeでは結果がすぐに表示され、リスク情報もあらかじめカテゴライズされているため、対応側としても判断がしやすく、作業時間のブレがほとんどありません。実際、1件あたりの確認時間は1分もかからないほどです。
加えて、コスト面のメリットも非常に大きく、月に1,000件、年間だと1万件を超えるチェックを継続的に実施している当社にとっては、費用対効果の観点でも非常に納得感がありました。こうした総合的な理由から、RiskAnalyzeの導入を決定しました。
多様な事業を支える全方位のリスクチェック体制とは
――幅広い事業を展開されている中で、どのような関係者をチェックの対象としているのでしょうか?
木下:当社では、従業員や役員のほか、販促事業で取引するメーカー企業、「クラシル」でレシピを提供してくださるクリエイターの方々やライバーさんなど、非常に幅広い関係者をチェック対象としています。
展開している事業が、レシピメディア「クラシル」やライフスタイル系メディア、販促アプリ、さらにはライバー支援まで多岐にわたるため、関わるすべての関係者に対してリスクチェックを行う必要があります。
――そのような多様な対象に対して、どのような体制でチェックを実施しているのでしょうか?
木下:運用体制としては、各事業部からのチェック申請が社内ワークフローを通じて上がってくる仕組みです。チェック作業そのものは外部パートナーに委託しており、結果はスプレッドシート形式でフィードバックされます。その後、コーポレートガバナンス部門が事業部と連携しながら、最終的なリスク判断を行っています。
判断基準については、一律のルールを設けているわけではなく、リスクの程度に応じて検討しています。たとえば、何かの記事がヒットした場合でも、その内容や背景を精査した上で最終的に、執行役員を含む関係部門がリスクの有無を慎重に判断しています。
――リスク判断にあたって、運用上の工夫や留意している点があれば教えてください。
木下:反社チェックに加えて、風評リスクのチェックも同時に行っています。特にライバーに関しては、本名のほかに活動名やチャンネル名などで検索をします。
ネット上の炎上事例や過去の投稿も確認することで、より実態に即したリスク評価ができていると感じています。
IPO準備から日常運用へ。信頼されるリスク管理の“標準装備”に
――IPO準備の中で、RiskAnalyzeはどのように役立ちましたか?
木下:上場にあたっては、コーポレートガバナンスや内部統制の体制が厳しくチェックされます。
RiskAnalyzeはその要件をクリアするために必要な機能をしっかり網羅しており、主幹事証券会社や証券取引所からもネガティブなコメントは一切なく、信頼性の高いチェック体制の構築ができました。
また、従来は手動で実施していた年1回の定期スクリーニングも一括で効率的に行える点や、検索結果の見やすさといった運用面での利便性も高く、社内での負担軽減にもつながっています。結果として、上場準備の中でも安心して導入・運用できるツールとして非常に役立ちました。
――そういった信頼性や利便性が評価され、 IPO後も継続していただいているのでしょうか?
木下:導入から3年が経ち、今ではRiskAnalyzeが業務の“標準装備”のような存在になっています。2024年にIPOをして以降も業務に自然に組み込まれ、日常的な運用の一部として定着しているので、今後も変わらず使い続けていくつもりです。
――社内外のやり取りに変化はありましたか?
木下:社内外の連携がスムーズになりました。特に、RiskAnalyzeの検索結果には一定のルールやリスク区分が設けられており、判断軸が明確です。そのため、外部委託先とも共通認識でやり取りができるようになりました。
以前は、検索結果の記載内容や表現にばらつきがあり、「関連があるかもしれない」といった曖昧な記述も多く、社内での解釈に差が出て判断に迷うことがありました。その点、RiskAnalyzeでは情報の出所や区分が明確に整理されており、社内での判断がしやすくなりました。結果として、業務効率が向上し、私たちは最終判断に集中できるようになっています。
自社の運用体制に合ったツールの選定が大切
――今後の反社チェック・コンプライアンスチェックの運用方針についてお聞かせください。
木下:今後もさらに取引先の増加が見込まれるため、チェック作業の効率化は引き続き大きな課題です。一方で、効率化のなかでもリスクチェックの質を落とさず、会社を守るという本来の目的を見失わないことが重要です。
その点、RiskAnalyzeのチェック精度には信頼を置いているので今後も「量」と「質」の両立を意識した運用を続けていきたいと考えています。
――RiskAnalyzeに対して、今後の改善や機能追加への期待があれば教えてください。
木下:一括スクリーニングを行う際に、企業名や代表者名の変更があった場合の対応については今後ぜひ改善を期待したいです。現在は過去データと照らし合わせながら、代表者名が変更されているかどうかを手作業で確認しています。件数が多いと、これがかなりの負担になるんです。
もし、RiskAnalyze側で企業データベースを自動参照し、昨年時点の情報と突き合わせて代表者名などの変更を検知、最新情報で自動的に置き換えてくれるような仕組みがあれば、業務効率が格段に上がると思います。
――ありがとうございます。最後に、反社チェック・コンプライアンスチェックのツール選定で悩んでいる企業へアドバイスがあればいただけますでしょうか?
木下:反社チェックコンプライアンスチェックのツールは多く存在しますが、「何が最適か」は企業の業態、業務フロー、社内体制、規模によって大きく異なります。単に記事量や網羅率だけで判断せず、自社の目的や運用体制に合ったツールかどうかを見極めることが非常に重要です。
私たちがRiskAnalyzeを選んだ理由のひとつも、「チェックの本質を見失わず、効率化を両立できる」という点でした。特にチェック件数が多い企業にとっては、社内の効率化は最も重要な軸だと思っています。