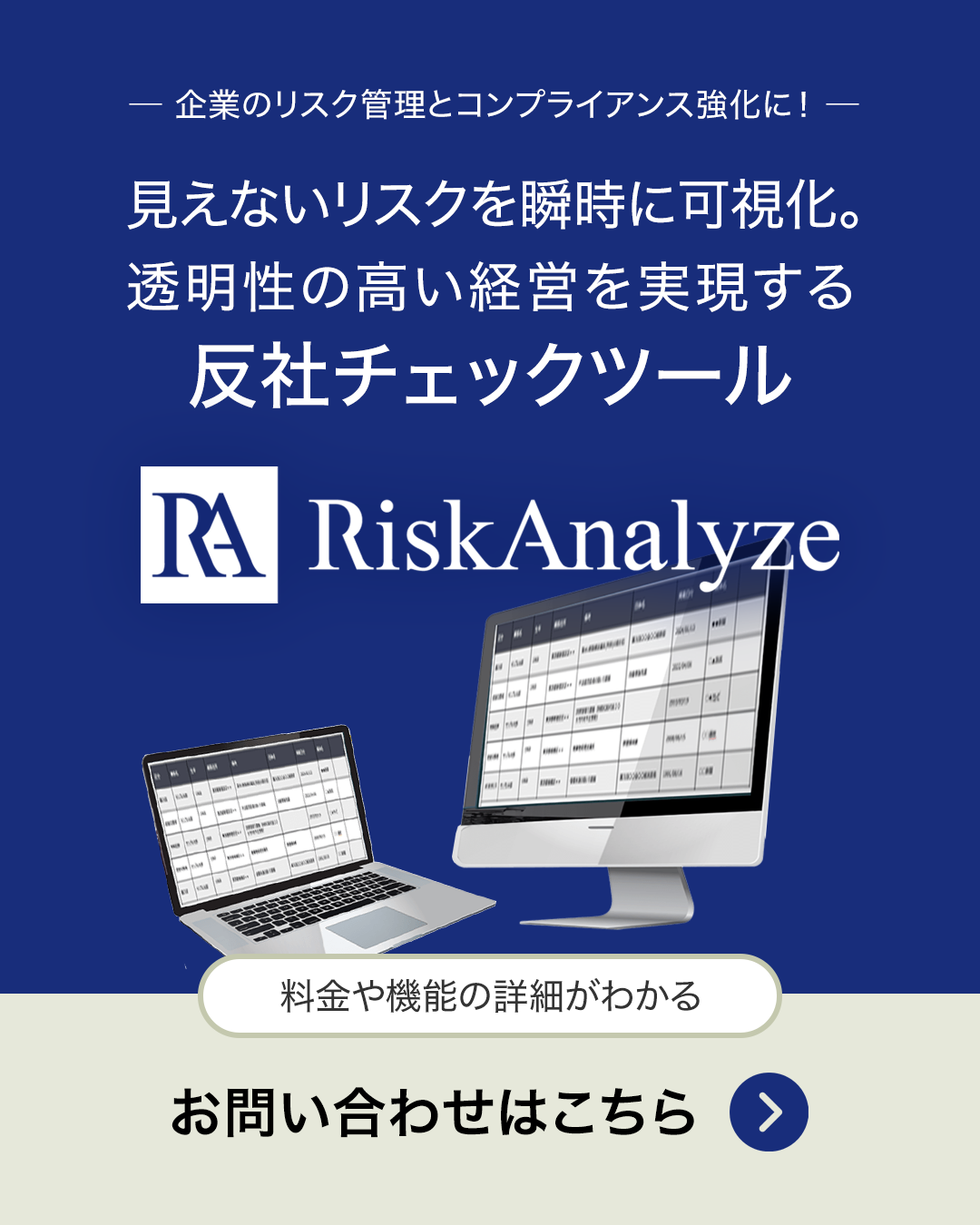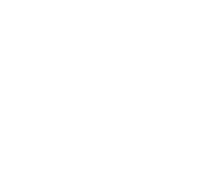月500件のチェックでも、大きな負担はなし。RiskAnalyzeが築く信頼の土台。
工事会社向け経営管理システム「クラフトバンクオフィス」を展開するクラフトバンク株式会社。同社が主催する建設業特化型のリアル交流会「職人酒場」は、職人不足が深刻化している建設業界において、新たな元請や協力会社・職人と出会える絶好の場として注目を集めています。
しかし、事業の急成長やイベント参加者の増加に伴い、より適切なリスク管理が求められるようになりました。そこで反社チェック・コンプライアンスチェックを徹底するために導入したのが「RiskAnalyze」です。今回は、導入の経緯や運用の工夫、今後の展望について、徳永様と平井様に伺います。

導入の決め手は“負担にならない”という確信。
――「RiskAnalyze」を導入するに至った経緯を教えてください。
徳永:クラフトバンクは、内装会社の新規事業部門からスピンアウトする形で2021年に設立されました。反社チェック・コンプライアンスチェックに関しては、分社化前から重要性を認識し、複数のツールを活用して対策を講じていたのですが、分社化後はネット検索や暴力運動追放推進センター(暴追センター)データを利用するなど、独自の運用方法で対応するようになったんです。
状況が変わったのは2022年後半。主力サービスである「クラフトバンクオフィス」の営業件数が急増し、さらに「職人酒場」を全国規模で週2回開催するようになったことで、従来の手法では対応が追いつかなくなりました。
そこで、あらためて適切なツールの導入を検討していたところ、株主であるAngel Bridge社から「RiskAnalyze」を紹介いただき、コストと運用のしやすさを考慮して導入を決定しました。
――過去に利用されていたツールと比較して使いにくさなどはありませんか?
平井:スムーズに利用できています。最近は多いときで月に500件近く検索をかけることがあるのですが、一括検索機能を利用すれば一度に何十件もまとめてチェックできるので大きな負担もありません。「職人酒場」の参加者チェックの効率が大幅に向上しました。
徳永:加えて、過去の検索結果をcsvとしてダウンロードして保管できる機能も非常に便利です。今後、上場準備が本格化する中で、履歴を残せることは大きな安心材料になります。運用面の不安が少ない点は、大きな評価ポイントですね。
噂がリスクになる業界だからこそ、チェックが会社を守ることになる。
―現在はどのようにRiskAnalyzeを運用しているのでしょうか?
徳永:職人酒場には運営チームがあり、事務局がWebサイトで参加者の募集を行っています。申し込みが入るとチャットツールにリストが自動投稿され、それをもとに平井がデータを整理し、一括検索用のCSVを作成して処理を進めます。
平井:チェックは、企業名と代表者名に加え、参加者個人の名前も対象にしています。以前は代表者と会社名のみで確認していたのですが、参加者個人が問題を抱えている場合、風評リスクが発生する可能性があるので対象を広げました。
――参加者個人までリサーチ範囲を広げるとなると、かなりの件数になりそうですね。
平井:検索がヒットしなければそのまま通過となり、ログが記録されます。検索でヒットした場合、まずは同一人物かどうかの確認を行います。同一性判断は非常に手間がかかりますが、ここを慎重に進めることで、より正確なリスク管理が可能になると考えています。
徳永:また、反社以外の犯罪歴についてもチェックしています。これは従業員の安全管理や他の参加者のリスク管理が目的です。
参加いただく方々に安心感を持っていただくためにも何か懸念があった場合に、「こういうプロセスを踏んで、こういう判断をした」という説明責任を果たせる状態を常に保つことが重要なんです。
そのうえで、反社チェックや過去犯罪歴の有無にかかわらず、イベントの利用規約に基づき、他の参加者に迷惑をかけるような行為があった場合は、次回以降の参加をお断りするという流れで運用を設計しています。職人酒場は件数が多いので厳密に対応していますが、他のケースでも基本的なフローは同じですね。
“やりすぎ”と思われても守りたい、信頼と安全のバランス。
――RiskAnalyzeを運用している中で困りごとはありませんか?
平井:現在のUIやCSVによる一括検索機能など、基本的な操作性には非常に満足しています。特に検索件数が多い「職人酒場」では業務負担の軽減に大きく貢献しており、現時点で大きな不満や課題は感じていません。
徳永:ただ、RiskAnalyzeの導入によってリスクチェックの精度が上がったことで、過去の判断とのギャップが生じることがありました。
これは悩ましい話ではあるのですが、手作業でチェックをしていた頃に問題なしと判断していた方が、RiskAnalyzeでヒットしてしまったんですね。
結果的に暴追データでヒットしなかったので問題はなかったのですが、判断に迷う場面でした。運用フローが変わることで社内の判断基準に変化が生じる課題とどうやって整合性を取っていくかが今後のテーマですね。
――具体的に取り組んでいることはありますか?
徳永:現在は審査フローの再整理を進めています。先ほど話したようなグレーなケースをこれまでは個別に判断していましたが、どうしても属人的な対応になりやすく、判断に一貫性を持たせにくいという課題がありました。そこで、一定のルールを設けて運用に落とし込む作業を進めているところです。
――最後に反社チェック・コンプライアンスチェックに対する今後の方針について聞かせてください。
徳永:現在、クラフトバンクは上場準備を進めており、運用負荷を考慮して初回チェックのみにとどまっていた運用体制を見直し、2024年10月から継続ユーザーに対する年次チェックも開始しました。より精度の高いリスク管理体制へと移行できたことで、監査法人からも「反社チェックが徹底されている」と一定の評価をされています。
今後も監査法人や証券会社、IPOコンサルタントと連携しながら、より実効性の高い運用体制を築いていく予定です。その一環として、今後もRiskAnalyzeを有効活用していければと考えています。