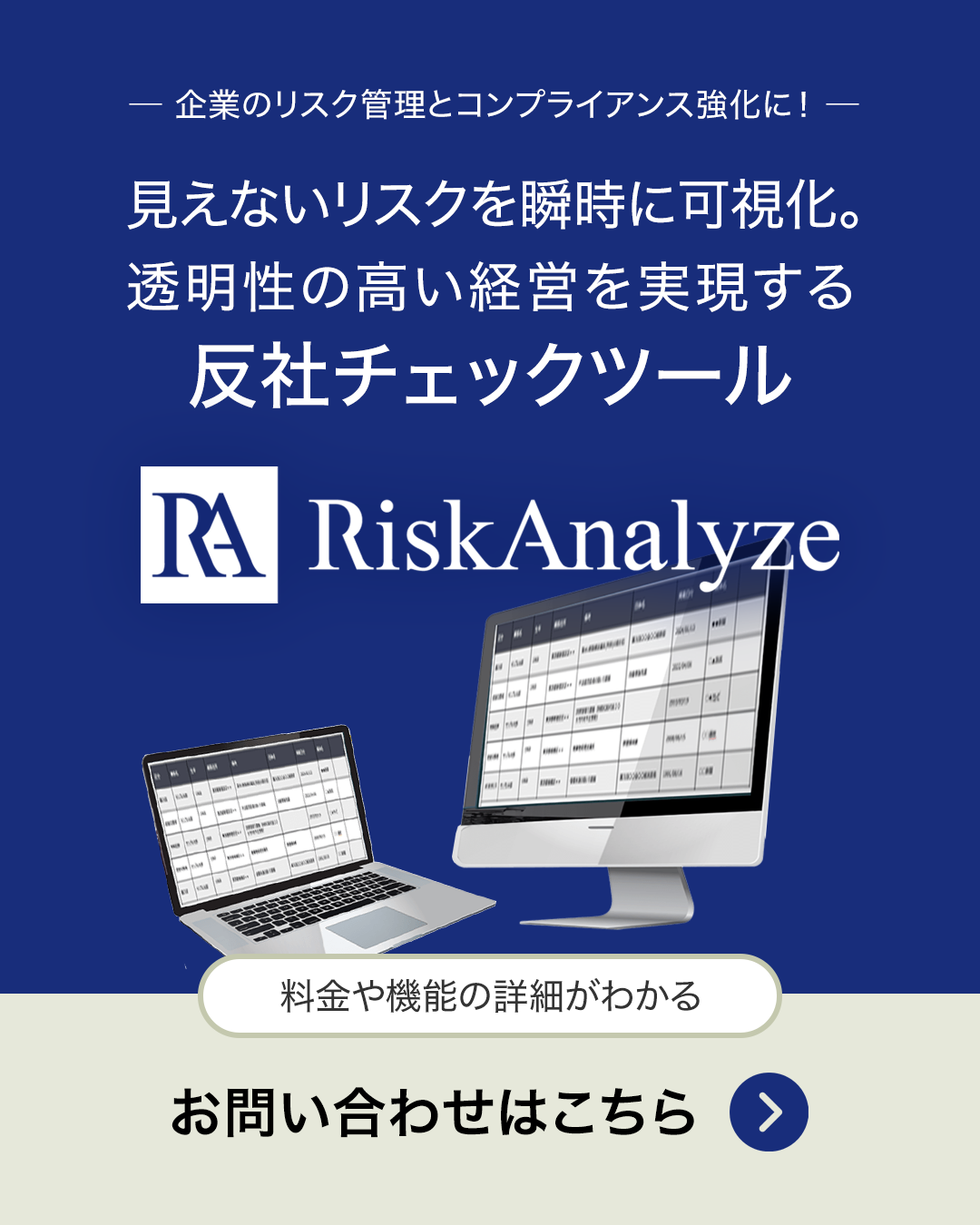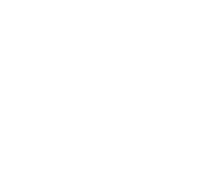人手は少なくても、見落としは許されない。VCが語る反社チェックの現場と工夫

ベンチャーキャピタル(VC)として数多くのスタートアップ支援を行っているAngel Bridge株式会社。2021年10月、反社・コンプライアンスチェックツール「RiskAnalyze」を導入し、翌2022年のAngel Bridge Unicorn Fund2号の立ち上げ以降、ファンドに加入するLP、投資先企業やその関係者への反社チェック体制を本格化しました。
限られた人員で多くの投資判断を下しているVCは、どのようにAML/CFT(マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策)と向き合い、実効性ある反社チェックを行っているのか。今回は運用実務を担う野末様に、導入の背景や運用フロー、LPへの対応、そしてチェックが投資判断に与える影響について詳しくお話を伺いました。
LPにとっても安心材料となる反社チェック体制の構築
――RiskAnalyzeを導入される前は、どのように反社チェックを行っていたのでしょうか?
野末:基本的には、Webを利用した手動検索です。名前にネガティブワードを掛け合わせて、過去の報道や評判が出てこないかを確認するという、いわば原始的な方法でした。投資件数が少ない間は何とか回っていましたが、2022年に投資事業有限責任組合(LPS)型のファンドを立ち上げたタイミングで、ファンドサイズも大きくなりスクリーニングすべき件数が増え、さすがに限界を感じるようになりました。
――2号ファンドの設立が、反社チェック体制を見直す契機になったのですね?
野末:そうですね。ファンドサイズが2倍となったこともあり、投資先企業の数が増えることが想定されていたことから、導入の必要性を感じました。創業時の匿名組合型のファンドから、適格機関投資家等特例業務の届出業者として、必要となるコンプライアンス対応は適切に実施してきましたが、LPS型に移行し機関投資家の加入が増えたことで、AML/CFTについて求められるレベルが更にワンランク上がりました。足元においても、社会全体で反社排除やマネロン対策の要請がさらに高まっていることを強く感じています。
――なるほど。現在はどのような範囲でチェックを実施していますか?
野末:投資検討時においては投資先企業の代表者・役員・主要株主が対象です。株主が法人の場合は、その法人の代表者まで遡って確認します。また、投資先企業に他のVCが含まれている場合は、ファンド名・運用会社・代表者の3つをそれぞれ検索するので、1社につき複数回のチェックが必要になることもあります。加えて、弊社では風評チェックも行いますので、その数は倍になります。
また、弊社のファンドが出資を受けるLP側のチェックも同様に必要となります。加えて、犯罪収益移転防止法に基づいた取引時確認を行っており、LP自身の実質的支配者やPEPs(外国政府等の要人)に該当するかどうか等について書面にて確認を行っております。ファンド運用者として当然の責務と考えております。
――法令対応に加えて、実務上でLP側からの要望を受けることもあるのでしょうか?
野末:あります。LPの方からは「反社チェックはどこまで対応しているのか?」といった質問をいただくことがありますが、「KYCコンサルティング社のRiskAnalyzeで、制裁リストやPEPs情報も含めて網羅的に確認しています」ときちんとご説明しています。そのうえで、「そこまでしっかり見ているのであれば安心」といったお言葉をいただくこともあります。
――LPにとっても、ファンドに安心して出資できる材料になっているということですね?
野末:そう思います。LPの中でも特に、金融機関や証券会社などの機関投資家については、AML/CFTに関する規制が年々強化されています。それに伴って、我々のようなファンドに出資する際に求められるAML/CFT体制も高度化しており、「きちんと反社チェックが行われていること」は出資判断にも大きく影響します。私たちのAML/CFT対応やコンプライアンス体制は、RiskAnalyzeのおかげで、「きちんとやるべきことをやっている」とこちらの体制が信頼に足るものであることをご理解いただけていると感じています。
――タイミングとしては、いつチェックを行っているのでしょう?
野末:LPについては、ファンドに申込をいただくタイミングで、投資先企業については、投資検討のタイミングで、チェックを実施しております。加えて、投資実行後でも資金調達時に株主の異動があるタイミングなどにおいては、再度チェックを行うようにしています。完全に“定期的”というよりは、都度必要に応じてアップデートしていく「随時更新型」の運用です。リスクは変化するものですし、一度見たから終わりではないという前提で、継続的に情報を確認する姿勢を大切にしています。
“飛ばせない仕事”を誰でも回せるように
――反社チェックを行うのは野末様おひとりでしょうか?
野末:はい、今は私が担当しています。反社チェック以外にもマルチタスクで様々な業務がある中において、反社チェックは“メインではないが、飛ばすことは許されない”業務です。とはいえ専任担当を置けるほど規模の大きな会社ではないため、チェック・記録・判断までを一人でも完結できる仕組みが必要でした。
そういった意味で、RiskAnalyzeは一連の流れが非常にシンプルで効率的に設計されているので、実務上大変助かっています。結局のところ、シンプルに勝るものはありません。
――実際、導入後の運用はどのように変わりましたか?
野末:まず、工数が圧倒的に削減されました。たとえば、検索結果は画面上ですぐに確認でき、CSVでの保存もできるので、投資検討資料に「この人物は3件ヒットしたが、生年月日が異なるため別人と判断」といった形でコメントを残し、記録に活用しています。こうした記録があることで、内部の意思決定プロセスにも透明性を持たせることができています。
――RiskAnalyzeを選んだ決め手はどこにあったのでしょうか?
野末:決め手は、求めていた情報がきちんと網羅されていること、そしてスピードと使いやすさですね。他のツールも比較検討しましたが、情報が細かすぎたり、価格が高かったりして「そこまでの情報量は必要ない」というものが多かったんです。RiskAnalyzeは「自分たちがやりたいことはすべて叶う」内容で、必要十分で実務に対して過不足がないと感じました。
特に、PEPsや海外制裁リストへの対応までカバーされていることは、銀行や証券会社などの機関投資家からの要請にも応えられる材料になります。
――現場で使いやすいと感じるのはどういった点でしょうか?
野末:検索のしやすさと結果表示の速さですね。叩けばすぐに結果が出てくるうえに、誰が操作しても同じ結果が出る安心感があります。結果はすぐ画面で確認できて、余計な手間もかからないです。
結果がリスク情報毎にカテゴライズされた状態で出てくるので、情報に対してどのようなリスクがあるのかが分かりやすい上に、判断が属人的にならないので誰かに引き継いでも同じクオリティで運用できる、というのもとてもありがたいです。
リスクを見逃さない。投資判断への影響とは
――RiskAnalyzeの検索結果が、投資判断に影響したことはありますか?
野末:あります。たとえば、過去に問題を起こした代表者や、属性に明らかな違和感のある株主が含まれていたケースなどです。風評チェックでアラートが上がった人物の情報を掘り下げる中で、完全な黒ではないもののグレーな状況で、「これは疑わしい」と判断して投資を見送ったこともあります。グレーな情報でも、疑念がぬぐい切れなかった場合には投資を見送る判断を下すこともあります。
――なるほど。数字や事業内容だけでなく、背景情報も重視されるのですね。
野末:そうですね。他にも、RiskAnalyzeの検索結果が、さらなる詳細調査のきっかけとなり、結果的に投資判断に影響を与えたケースもあります。たとえば、ある投資先企業の株主に、過去に不適切な資金のやり取りに関与していたとされる子会社を持つ企業がいたのですが、その情報がRiskAnalyzeでヒットしました。
このような場合はすぐに投資を中止するわけではなく、その問題が現在も継続しているのかどうか、子会社がすでに清算されているか、当時の代表者が退任しているかなどを具体的に調べます。適切に対処されたことが判断できれば投資に進むこともありますし、問題が解消されていないと判断した場合には、見送る判断をすることもあります。
――最終的な判断はどのようにしてらっしゃるのでしょうか?
野末:もちろん最終的な判断は、RiskAnalyzeの結果だけで決まるわけではありません。ツールの情報に加えて、Web検索の結果や業界内での評判、周りの人からのリファレンスなど、非公式な情報も含めて総合的に判断しています。RiskAnalyzeはあくまで中立的かつ網羅的な材料としての役割を担ってくれており、特に「この人物は気になる」と思ったときに検索結果が情報の厚みを与えてくれる点で、投資判断プロセスの重要な位置づけになっています。
少数精鋭な企業こそ、確かな仕組みが力になる
――今後、RiskAnalyzeに期待する機能はありますか?
野末:継続的にリスク情報を検知して通知する「自動モニタリング機能」ですね。今日“白”だった人物が2週間後に“黒”になる可能性もあると思うので、RiskAnalyzeにその機能が実装されれば、さらに強固なチェック体制を構築できると思います。
あとは、複数名を一括で検索できる機能もあると嬉しいですね。今は個別で社名・役員名・株主名を入力していますが、これらを一つのグループとしてまとめて検索できると、効率がさらに高まります。
――ありがとうございます。最後に、RiskAnalyzeの導入を検討している企業に向けてメッセージをお願いできますでしょうか。
野末:反社チェックは一見地味で、つい後回しにされがちな業務かもしれません。しかし、我々のような投資家の大切な資金を預かるファンド事業者においては、信頼性を支える根幹を担う部分であり、万が一のリスクを未然に防ぐうえでも、軽視できない領域です。とはいえ、私たちが少人数体制で、多岐にわたる業務を担っているように、同じような規模の企業にとっても、反社チェックに過剰な工数を割くのは難しいのが実情ではないでしょうか。
その点、RiskAnalyzeは非常にシンプルかつ確実な仕組みで、必要なチェックが“叩けばすぐに出てくる”形で完結できます。本来注力すべきコア業務に集中できる環境をつくるうえで、欠かせない存在です。まずは、自社にとって“必要最低限の信頼性”を効率よく担保する手段として導入し、自社の実務と自然にフィットするかを試してみるのが良いと思います。